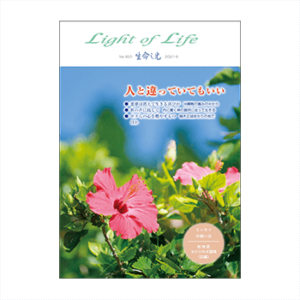エッセイ「母が伝えてくれたこと」
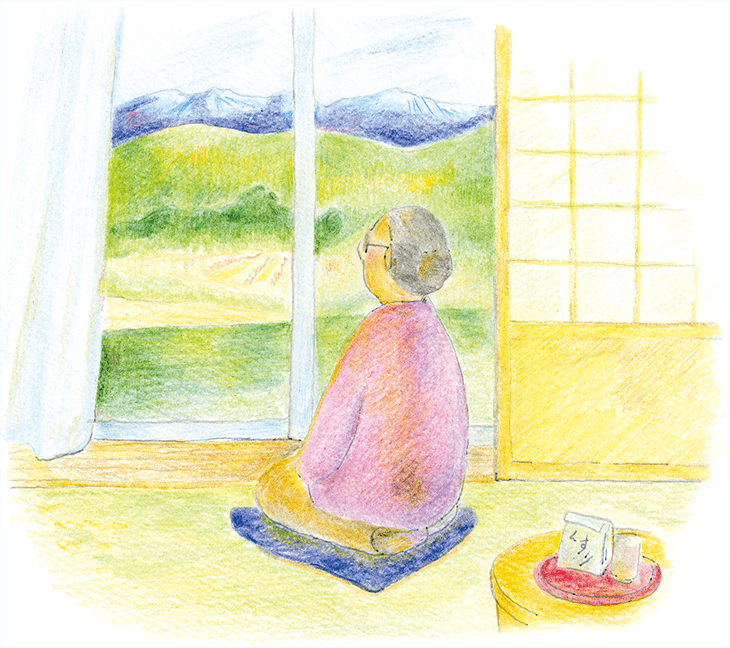
千葉賛子(よしこ)
「自然死の大往生です」。そう言って、お医者さんから母の臨終を告げられました。いつ息を引き取ったのかわからないくらい静かで、穏やかな最期でした。母と同居を始めて9年目の、今年1月のことでした。
東日本大震災が起こった年の12月に父が亡くなり、母は仙台から、長野県に住む長女の私のところに身を寄せました。そして、3年前に運転免許証を返納したころから、母の認知症が少しずつ始まってきました。
私は教員をしていまして、昨年の夏に母をショートステイに預け、修学旅行の下見に行きました。コロナ禍の中で県外に出たので、隔離のため2週間、母との接触ができなくなりました。その後から、母のようすがそれまでと違うな、と思いはじめました。
そして、11月の修学旅行でまた接触ができなくなると、いよいよ母の反応がなくなってしまいました。
「お母さん、歯磨きした?」と聞いても、ボーッとしているんです。私の夫のことを「お兄さん」と呼ぶなど、その数カ月で急激に認知症が進んでしまいました。外出しないように靴を隠したり、息をしているかなと夜中にようすを見ながら、母と過ごしてきました。
最期をどう迎えるか
昨年末のことでした。デイサービスの方から、母が食事をほとんど摂(と)らず、身体(からだ)も弱ってきていると言われました。そして、「最期をどうしようと考えておられますか。入院して延命治療をしますか。それとも、デイサービスに通いながら、最期を自宅で看取(みと)りますか」と聞かれたのです。
一瞬ドキッとしたのですが、「私のほうで最期まで看たいと思います」と言いました。その時、死ということを身近に感じ、母が、そして私もどういう最期を迎えるのか、を考えさせられました。
若いころにキリストに出会い、以来60年間、信仰一筋に生きてきた母が、「わが人生に悔いはない」と言い切ったその心情を知りたいと思いながらも、忙しくて後回しになっていました。
「あなたたちに遺(のこ)せる財産は何もない。遺せるものはこの信仰だけ。これを受け継いでほしい」と、私たち三姉妹に真剣な表情で迫ったこと。
朝から大声で賛美歌をうたい祈る父母に、「友達に聞かれると恥ずかしい」と言ったら、毅然(きぜん)として「何も恥ずかしいことはしていない」とはねのけられたことなど、母と過ごした時のことが思い出されます。
見えない世界につながれて
ある朝、そんな母が急に、「感謝で、感謝で……」と言って大泣きしているんです。「何が感謝なの?」と聞いても、答えはありません。
ところがその日の午後に、母が仙台に嫁いだころから共に祈り、励ましてくださった方が亡くなられた、という連絡が入ったのです。施設で寝たきりだったそうですが、最期は天を見つめて、大平安の中で召天された、とのことでした。その方が亡くなられたことを、母は直感したのだと思いました。
日常会話はできなくても、祈ると感謝の言葉しか出てこない母を見ると、神様と共に生きてきた信仰が、晩年にはそのまま表れてくるのだと知りました。ごまかしのきかない生命の世界だと思うと、私ももっと、魂の会話ができる者になりたいと願いました。
母が亡くなる前日、賛美歌をうたって祈りました。「お母さん、帰るところはキリストの神様のところだね」と言うと、すぐに反応し、はっきりと頷(うなず)きました。母は何もできなくなっても、最後の一息まで神様の愛に生きつづけることを伝えたかったのだと感じました。
ほほえんでいるようにも見える母の死に顔を見つつ、神様の愛が私の胸にも脈打ってくるのを覚えました。
今は、天が慕わしくてなりません。
本記事は、月刊誌『生命の光』819号 “Light of Life” に掲載されています。