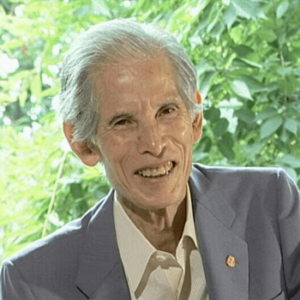聖書講話「すべてを許す愛」ヨハネ福音書13章18~30節
人間は互いに愛し合い、信じ合っていても、その愛や信頼が裏切られることがあります。そんなとき、「真実の愛」とは何か、と求めます。
イエス・キリストは弟子の一人、イスカリオテのユダに裏切られ、十字架上に死なれました。他の弟子たちも、師を捨てて逃げてゆきました。しかし、すべてを知りつつ彼らを許した真実の愛。また、裏切るような人の心をも変えてしまう神の生命を、ヨハネ福音書は説いています。(編集部)
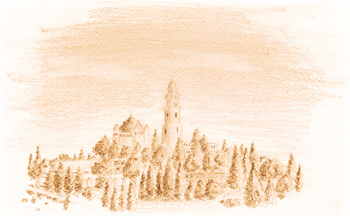
「わたしは自分が選んだ人たちを知っている。しかし、『わたしのパンを食べている者が、わたしにむかってそのかかとをあげた』とある聖書は成就されなければならない。そのことがまだ起らない今のうちに、あなたがたに言っておく。いよいよ事が起ったとき、わたしがそれであることを、あなたがたが信じるためである……」。イエスがこれらのことを言われた後、その心が騒ぎ、おごそかに言われた、「よくよくあなたがたに言っておく。あなたがたのうちのひとりが、わたしを裏切ろうとしている」
ヨハネ福音書13章18~21節
イエス・キリストは十字架にかかられる前夜、弟子たちの足を洗い、弟子たちを極みまで愛されました。だが、悪魔が弟子のユダの心にイエスを裏切る思いを入れていた。21節に、「その心が騒ぎ」とありますが、ギリシア語では「πνευμα プニューマ(霊)が騒ぎ」という言葉です。キリストの霊が動揺し、騒ぎ立ったのです。心の奥深いところに霊魂があります。その霊魂が騒ぎ立った、という。愛する者が悪魔に奪われるのを目の前で見られた時に、キリストの霊は騒がざるをえなかったのです。
これは、伝道する者がひとしく経験することです。愛している者が、悪魔にみすみす奪われてゆく。どんなに言い聞かせても、どんなに尽くしても、もうわからない。石のように心が硬くなってしまっているからです。これは心が騒ぐくらいじゃない。心の奥の、潜在意識のもっと奥底の霊が騒ぎ立って、どんなに苦しいかわかりません。
また、イエス様は神の子だから、どんなときでも平静で不動なお方だと思う。けれども、生きているものはすべて、騒ぐんです。生きていればこそ、いろいろな不安に、危険に、困難にさらされたときに動揺するのです。動揺するのは生きている証拠です。動揺もせず、行ない澄ましたような者がクリスチャンだと思うなら、大変な間違いです。キリストですら霊が騒ぎ立ったというのならば、私たちの霊が騒ぐのは当然のことです。
内なる霊が騒ぐのを押し殺していたら、サタンとの戦いに勝てません。サタンのいい餌食です。もし私たちの霊が騒ぐことがあるならば、その背後において何かが始まっていることを知らなければなりません。
自分を裏切る者に対しても
弟子たちはだれのことを言われたのか察しかねて、互いに顔を見合わせた。弟子たちのひとりで、イエスの愛しておられた者が、み胸に近く席についていた。そこで、シモン・ペテロは彼に合図をして言った、「だれのことをおっしゃったのか、知らせてくれ」。その弟子はそのままイエスの胸によりかかって、「主よ、だれのことですか」と尋ねると、イエスは答えられた、「わたしが一きれの食物をひたして与える者が、それである」。そして、一きれの食物をひたしてとり上げ、シモンの子イスカリオテのユダにお与えになった。
ヨハネ福音書13章22~26節
「わたしを裏切ろうとしている」とイエスが言われたので、弟子たちは誰のことを言われたのだろうかと、当惑したのです。それで互いに見合った。
ここで「イエスの愛しておられた者」というのは、たぶんヨハネ福音書を書いたヨハネのことと思われます。「み胸に近く席についていた」と書いてありますが、ギリシア語の原文を読むと「席にもたれかかって、(イエスの)懐の中にあった」とあります。
当時は、椅子に腰掛けて食事するのではなく、行儀が悪いようだけれども、横になって足を投げ出して食べたんですね、こうやって(実際にやって見せる)。それでこの弟子は、イエスの懐の中にもたれかかるようにして寄り添っていたということでしょう。
シモン・ペテロは「おいおい、先生は妙なことを言うぞ」と思って、ヨハネに「誰のことをおっしゃったのか知らせてくれ」と目で合図したんでしょうね。それで、ヨハネはそのまま顔だけ前を向いてイエスの胸に倒れかかって、他の弟子に気づかれぬように小声で、「主よ、誰のことですか」と聞いたのでしょう。
イエスは、「わたしが一切れの食物を浸して与える者が、それである」と言われた。「浸す」とは、過越の祭(注)で食べる、果物を煮詰めた汁に浸すことでしょう。また、それを与えるのはあちらの慣習で、「さあ、これをお食べなさい」という大事な人への愛情表現です。イエスは、「特別に愛しているよ」ということをユダに言おうとされたのです。周囲の者も、まさかいちばん愛されているユダが裏切るとは思わなかったでしょう。イエスはユダの心を見抜いておられたでしょうが、自分を裏切る者に対してまでも、最後までその人が傷つかないように慮(おもんぱか)っておられたことがよくわかります。
(注)過越の祭
聖書の時代からの、イスラエルの重要な祭りの一つ。春に行なわれ、出エジプトと呼ばれる、古代エジプトの奴隷状況から解放された民族の救いを記憶する。その故事に従い、1週間の間、酵母を入れないパンを食べる。

すべてを知ることは、すべてを許すこと
この一きれの食物を受けるやいなや、サタンがユダにはいった。そこでイエスは彼に言われた、「しようとしていることを、今すぐするがよい」。席を共にしていた者のうち、なぜユダにこう言われたのか、わかっていた者はひとりもなかった。ある人々は、ユダが金入れをあずかっていたので、イエスが彼に、「祭のために必要なものを買え」と言われたか、あるいは、貧しい者に何か施させようとされたのだと思っていた。ユダは一きれの食物を受けると、すぐに出て行った。時は夜であった。
ヨハネ福音書13章27~30節
それまでユダは、イエスを「先生」と呼んで頼っていましたし、イエスから信頼され、財布まで託されるほどだったのに、なぜ裏切ったのでしょうか。
ある文学者が「私がもしキリストであったら、ユダを作らなかったであろう。キリストといえども、ユダを作ったところに失敗がある」と言っております。しかし、キリストはユダが裏切る最後の最後まで愛を示して、一切れの食物を渡し、「さあ、これを食べなさい。わたしは強制しないよ。おまえのしたいことをしなさい」と、裏切る自由までユダに許しておられます。
私の好きな言葉があります。フランスの有名な格言で、「すべてを知ることは、すべてを許すことである」。それは愛ということです。
古代キリスト教最大の教父であるアウグスチヌスも、「真に知るということは、愛において知ることである」と言っております。愛がなかったら、知ろうとする相手は心を閉ざしてしまう。たとえば、一人の女を男が愛するとする。もし真に愛してくれたならば、女は真っ裸になって男の前に立ち現れることをもいとわない。しかし、愛のないところでは、自分の衣を脱ごうとはしない。愛だけが自分を現させる、というのです。
愛がなければ、相手をほんとうに知るということはできません。イエスはユダを愛しました。そして、すべてを許していました。ご自分を任せていました。イエスにおいては、裸になるぐらいの任せ方ではない、牢屋に入れられて、十字架に殺されることすらも許しておられました。
自分が裏切られ、十字架にかかって殺されることすら許すほどの心がある人は、ほんとうに人を知ることができます。しかし、お互いに心を閉ざし、警戒し合いながらでは、知ろうとしても知ることはできません。
「すべてを知ることは、すべてを許すことである」とは、なんと含蓄のある言葉でしょうか。イエスがユダの心の奥の奥までご存じだったのは、もちろん預言者的な洞察力もあるでしょうが、ユダにご自分のすべてをゆだね、すべてを許していたからです。
それで、人をよく知ろうと思うならば、許すことが大事です。許すということは、こらえる、という程度ではない。自分がめちゃくちゃになることをすら許す、という意味です。
ですから、伝道ということは、裏切られることを覚悟せずにはできません。あんなに愛した人が、こんなにひどいことを自分にするのか、と思うこともあるのです。
魂が目覚めなければ愛もわからない
ユダはイエスのそばにいて深く愛されながら、なぜイエスのお心がわからなかったのだろうか、と思います。しかしこれは、ユダだけではないですね。ペテロだってイエスから、「鶏が鳴く前に、あなたは三度わたしを否む」と言われました。みんな五十歩百歩です。今、講義している私も、ペテロやユダになりかねません。これはいったいどうしてか。
私は一晩じゅうこの聖書の箇所を考えていて、明け方に霊感されたことがありました。それは、「人間には心の奥に霊というものが、魂がある。そして、人類が全被造物のうちで最も尊いのは、神の性質である霊がその肉体に宿ったからである。しかし、霊魂は物質である肉体に宿ると、非常な制限を受ける。それで霊が宿っても、ほとんどの人においてその霊は葬られたような、眠ったような状況である」ということです。
目覚めない者は、この地球での生活が終わったらすべてが終わると思うから、あくせくして、少しでも長生きしようと、お金を貯め、地上が花だと思って、もう一生懸命です。けれども霊が目覚めだしたら、真の自分、すなわち霊魂は肉体という仮の宿に留まっているけれども、霊は永遠に生きつづける存在であることを自覚します。これを自覚しだした魂は惑いません。また、ほんとうに幸福です。
動物にしかすぎない人間の奥深くに宿った霊魂、これが揺り動かされて目覚めることがある。魂が目覚めるとは、永遠の光に、天使たちが生きているような雰囲気に目覚める、下界にありながら天国に目覚める、ということです。魂が目覚めない間は、尊いイエス・キリストと一緒に食事をしながらも、その有り難さも御愛もわかりません。心が闇だからです。「ユダはすぐに出て行った。時は夜であった」とあるように、心の闇、これはほとんどの人間の置かれた状況ではないでしょうか。ユダは闇の中で信仰していた。ペテロもそうでした。真っ暗な中では、どんなに愛を示されても目覚めることはなかったのです。
しかし、聖霊の光に浴すと、私たちの肉体に神のごとき心、聖霊が宿るという経験を自覚し、新しい生まれ変わり、「新生」が起こって、全然違った境涯が始まります。
聖霊の光に照らされよ
ヨハネ福音書を読みながらずっとお話ししているのは、信仰には真っ暗な中で信じる信仰と光の中で信じる信仰がある、ということです。真っ暗な中で信じる人は、躓(つまず)き、惑い、苦しみ、何が本当かと案じます。しかし、光の中で信じている人は、明々白々、すべてがお見通しだから、まごつくことはありません。光の中に生きている人は信じたごとく成る。信じたごとくすべてのことが展開してゆく。こういう信仰を確立しなければなりません。
キリストは言われた、「われに従う者は暗き中(うち)を歩まず、生命の光を得べし」と。生命の光をもって生きることを、信仰というのです。だから大事なことは、聖なる光を注がれるという経験を豊富にすることです。そうでなければ、力ある信仰になりません。
それで、神の光の中に入って生きてゆくために、私たちはこうやって集まって聖書を学び祈るのです。他の人たちが、この光をもっている人を見ることを通して、「なるほど」とその光を悟り、光に入ってきます。信仰する心は、みんなの潜在意識にはありますよ。しかし光を与えなければ、それが芽生えません。
イエスは「われは世の光である」と言って、光を与えるために世に来られた。また、「汝ら光の子とならんために、光を信ぜよ」と言われました。信仰とは、キリストから発散する霊的な光、真っ暗な心の闇を破ってくれるものを発見することである、とヨハネ福音書は言うのです。光の中で信仰しはじめると、ほんとうに驚くべきことが次々と起こる。だから、私たちは日々聖なる光を注がれて、「日ごとに奇跡を見させたまえ」と祈らねばなりません。光が不思議なことをなしてゆくからです。
(1964年)
本記事は、月刊誌『生命の光』2020年3月号 “Light of Life” に掲載されています。