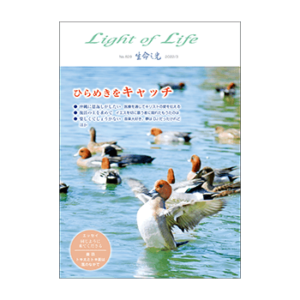聖書講話「復活の主を求めて」ヨハネ福音書20章13~23節
イエス・キリストは、十字架上に死んだと思われたが、墓を蹴破って復活されました。復活のキリストは、今も霊として生き、悩んでいる者、苦しんでいる者に現れ、救いたまいます。復活の主を慕いつづけ、生けるキリストに触れるならば、暗い現代に希望を点ずる者となれるのです。
今回は、晩年に差しかかった手島郁郎がヨハネ福音書を通し、復活節(注1)で語った講話の抜粋です。(編集部)
(注1)復活節
復活祭ともいう。十字架にかけられたイエスが、3日目に復活したことを記念し祝う祭り。毎年春ごろに行なわれ、キリスト教において最も重要な祭りとされている。
イエス・キリストの弟子たちは皆、イエスが十字架上に死にたもうた後、ユダヤ人たちの迫害を恐れて、扉を堅く閉ざし、恐怖と不安に明け暮れておりました。弟子たちはイエスを、「この人こそメシア(救世主)である」と信じて慕い、家も職も財産も捨てて、3年間というものお従いしてきたにもかかわらず、最も大切な方が、あえなく処刑されて死んでしまった。すっかり希望と光は失(う)せ、もう何も信ずることができなくなりまして、人目を忍んで潜伏していた。これが十字架の日以後の状況でした。
希望を失い、暗い部屋に閉じ込められたような状況、現代の暗い世相を見ると、今の時代もこの時と同様と思います。しかし、だれかが扉を開いて、光の世界に突入しなければなりません。時代が暗ければ暗いほど、どこかに必ずそのような人が出てきます。それは、どんな人だったろうか? ヨハネ福音書20章にそれが記されています。
イエスが十字架にかけられて3日目の、週の初めの日、朝早く暗いうちに女弟子のマグダラのマリヤが、イエスの葬られた墓に行くと、墓から石が転がしてあって、主イエスの亡骸(なきがら)が取り去られていました。マリヤは驚いて、走って弟子のペテロとヨハネのところへ行き、「だれかが主を墓から取り去りました」と言って、事の次第を伝えました。この2人はすぐに走って墓に行って見たが、墓が空っぽなのでそのまま帰ってしまいました。
しかし、マリヤだけは帰らずに、一人墓の外に立って泣いておりました。男の弟子たちは「しかたない」といってさっさとあきらめて帰っても、マリヤはとても家に帰る気がしなかった。かつて7つの悪霊に憑(つ)かれて狂い、ヒステリー状況だった悲惨なマリヤ。だが、ひとたび主イエスに触れまつってからというもの、拭うように清められ、救われた現在の自分を思えば、師と仰ぐ御主の面影を偲(しの)び、一人さめざめと泣き暮れていたのでした。
第三者の気持ちなら泣きません、客観的神学で神を詮索する人たちは泣かないでしょう。しかし、マリヤは身がよじれるほど痛み悲しみました。最愛の主を失い、せめて亡骸にでも触れまつりたい、と慕って来たのに! 亡骸があったとて救われるものでもないが、信仰は理屈ではありません。人間が自分の全存在をかけて生きる時に、理屈は通りません。
立ち去りがたくして、身を屈(かが)めて墓穴をジッとのぞき込んでいると、突然に彼女は不思議なものを見ました。あそこに一夜でも主は横たわりたもうたのだ……と、ゆかりの場所を見つめていた時、マリヤの目にありありと映ったのは、白く輝く2人の御使いでした。

天使を見ても
すると、彼ら(御使い)はマリヤに、「女よ、なぜ泣いているのか」と言った。マリヤは彼らに言った、「だれかが、わたしの主を取り去りました。そして、どこに置いたのか、わからないのです」。そう言って、うしろをふり向くと、そこにイエスが立っておられるのを見た。しかし、それがイエスであることに気がつかなかった。
ヨハネ福音書20章13~14節
真っ暗な気持ちで泣いていたマリヤ。彼女は、亡骸の主イエスでもいい、もう一度お会いしたい、と切なる思いで願いつつ見ていたのでしょう。その時現れたのはイエスでなく、天使でした。暗い穴に光り輝く神の御使いが座っていた。この驚くべきビジョンを見たのですから、彼女は大喜びすべきです、「ああ、私はついに天使を見た!」と言って。しかし、天使を見ること以上にマリヤがひたぶるに求めていたのは、キリストご自身でした。
私はこのたびの復活節が来ることを、内心恐れておりました。昨年来、ずっと体の調子を崩しており、体が重くだるいと、心も鉛のように沈んで重くなります。このような暗く沈んだ人間が、キリストの復活を説くと言いましても、口先だけの説明ごとになる。そんな偽りの伝道をしたくないと思うと、復活節を迎えることが心に負担となってきました。
私は自分の心に、マリヤのように純粋でひたぶるな気持ちがあるかどうかを問うてみました。長年の疲労のために、体全体が浮腫(むく)み、意識が朦朧(もうろう)としています。心が疲労すると、人間は虚脱状態になって新鮮な感情を失い、冴え渡った思想、豊かな情感がわいてきません。まして、マリヤのように見えないものを見透す力をもつことはできない。何も魂に訴えず、物憂いのが私です。イエスの第一の弟子ともいうべきペテロ、ヨハネたちでもそうでした。マリヤを残してさっさと帰ってしまいました。
マリヤは、天使を見るという不思議なビジョンに接したのですが、それで満足しませんでした。そして、目指す者を求めて悲しみの涙に暮れているマリヤの背後に立ちたもうた方がありましたが、彼女は気がつきませんでした。
「ラボニ! わが大師よ!」
イエスは女に言われた、「女よ、なぜ泣いているのか。だれを捜しているのか」。マリヤは、その人が園の番人だと思って言った、「もしあなたが、あのかたを移したのでしたら、どこへ置いたのか、どうぞ、おっしゃって下さい。わたしがそのかたを引き取ります」。イエスは彼女に「マリヤよ」と言われた。マリヤはふり返って、イエスにむかってヘブル語で「ラボニ」と言った。それは、先生という意味である。イエスは彼女に言われた、「わたしにさわってはいけない。わたしは、まだ父のみもとに上っていないのだから」
ヨハネ福音書20章15~17節
マリヤは悲しみのあまり、それが主イエスだとは気がつきませんでした。彼女はてっきり、主を葬ったアリマタヤのヨセフの家来が墓番をしているのだ、と錯覚しました。
イエスが、「女よ、なぜ泣いているのか。だれを捜しているのか」と問われても、マリヤは「もしあなたが、あのかたを移したのでしたら、どこへ置いたのか、どうぞ教えてください」と、とんでもない反問をしました。
しかし、イエスが続けて「マリヤよ!」と呼びかけられた時に、マリヤはその声に驚いて振り返り、「ラボニ!」と言いました。「ラボニ」とは「私のラボン」という意味です。普通は「先生」を「ラビ」と呼びますが、「ラボン」はもっと偉い「大先生」のことです。四国のお遍路さんは、弘法大師を「お大師さん」と呼んで慕いますが、マリヤにとっても主イエスは「おお、私の大師よ!」と言って敬慕する対象なのでした。
泣きの涙で見ているうちは墓番くらいにしか見えなかったが、主の声を聴いた時、彼女はかつて7つの悪霊に憑かれて忌み嫌われていた自分に、「マリヤよ、マリヤよ」と声をかけて慈しみ導かれた、あの懐かしい御声をハッと悟った。「マリヤよ!」と一声呼ばれた一瞬に、彼女は悲しみのドン底から蘇生しました。
キリストであることがわかって触ろうとすると、「触ってはいけない」とイエスは言われた。イエスのご生前、ベタニヤ村のラザロという男が死にました。死んで4日もたっていたのに、イエス・キリストが墓穴に向かって「ラザロよ、出てこい!」と呼ばれたら、ラザロは包帯を巻いたまま出てきた、ということがありました。その時のラザロとご自分の復活とが本質的に違うので、イエスは彼女に注意されたのでしょう。
ラザロは一度よみがえったが、やがて死にました。しかし、イエス・キリストの復活は、単に肉体が生き返ったのではなく、肉体ごと霊的な栄光体へ復活されたのでして、今も生きて、呼べばこたえるように、悩める者、くずおれる者のそば近くに来たり、助けたまいます。
今も呼びかける御声
私はこの物語を瞑想し、思いにふけっているうちに、ハッとしました、
「手島郁郎よ、おまえが幼い時から、わたしは幾たびおまえを憐れんで、導いてきただろうか」と。戦時中、軍の牢獄から救出され、また戦後、アメリカ軍政官の追及を受けて阿蘇の山奥に逃げた時にも、涯なき荒野の奥で救われたではないか! あの時、私はキリストの御声を聴きました、「わたしはおまえに、悩みのパンと苦しみの水を与える。このことに耐える覚悟ができるならば、おまえを教える者は再び隠れることがない。おまえの目は、常にその教える者を見るだろう。おまえが右に行き、あるいは左に行くにも、その後ろ辺から『これが道だ、これに歩め』という言葉を耳に聞くだろう……」と。イザヤの預言が肺腑(はいふ)を貫くように刺し込み、まばゆい主の臨在に接したことがあった。
ああ、そうでした。日ごと夜ごとに祈れば、いつも鮮やかに主の臨在を感じていた私でしたのに、今は床に就いたまま一人身動きすることも物憂い自分。だが急に、「マリヤよ」と呼びたもうたのと同じ御声が、「手島郁郎よ」と言って呼びたもうのを感じました。
「ああ、主よ! 私の大師イエスよ!」と叫ぶと、お慕いしてやまない主イエスの息吹が……みずみずしい感情が泉のようにわき上がり、身も心も、力がよみがえってきました。急に一転して心ときめき、力が全身にみなぎってくるのを感じました。
「神様、私は復活節の集会に行きます。主よ、どうかそこで、泣き悲しんでいたマリヤを呼びたもうたように、集う兄弟姉妹に呼びかけてください」と祈りました。
今、イエス・キリストについて研究されたり、議論がたたかわされたりしています。しかし、どうでしょう。マリヤが「ラボニ!」と言ってひたぶるに慕ったように、キリストを求めてお慕いしているのかどうか? 彼女にとっては、キリストさえあれば十分でした。男の弟子たちは空(うつ)ろな墓を見ても、平気で帰ることができたかもしれないが、マリヤはもう、キリストなしには生きられぬ人間になっていました。
イエス・キリストが復活の霊姿を第一に現されたのは、泣き悲しんでいるマリヤに対してでした。墓の番人と思っていた人から、「マリヤよ」と一声呼びかけられた時、彼女はハッと自分を取り戻した。目覚めた魂には、ありありとキリストの御姿が映し出された。
肉眼で姿を見ること以上に、イエスの御声を聴くことのほうが彼女に救いとなりました。それならば私も、今ここに集う一人ひとりに、主ご自身が親しくその名を呼んで、あなたの御前に立たしめたもうよう祈り願います。おお主よ、わが心の眼を、耳を開きたまえ!
復活の信仰に生きる者
「ただ、わたしの兄弟たちの所に行って、『わたしは、わたしの父またあなたがたの父であって、わたしの神またあなたがたの神であられるかたのみもとへ上って行く』と、彼らに伝えなさい」
ヨハネ福音書20章17節
ここに「わたしの兄弟たち」とありますが、ペテロ、ヤコブ、ヨハネたち──十字架を前にして一度はつまずいて主イエスを見捨てた人間ですのに、そんな者たちに「わが兄弟よ」と言って、主は御愛の御声をかけたまいます。
「マリヤよ、行ってわたしのことを伝えよ! わたしは、死んでも死なない、今も生きている。いよいよ天に昇ってゆくぞ」と命じて、彼女に使命を託されました。
復活のキリストに接するという出来事は、ただ単に自分が慰められ、救われるだけではありません。復活の信仰を抱いた者には、神から新しい使命を託されます。今まで悲しみに打ちひしがれて泣いていたマリヤ。しかし、彼女によみがえりの朝が訪れると、主の復活を告げる使命が与えられ、活き活きとした希望の再出発ができました。
マリヤのように、目に見えないものを見ることが信仰です。ヘブル人への手紙11章に「信仰とは、望むところを確信し、いまだ見ていないものを真実とすること」とあります。天国のかなたは見えません。しかし、見えないものを見、未来を予見し、現在の意識を拡大して、ヴェールに隠されたはるかかなたをも見透す力──これを信仰といいます。
偉大な発明、発見においても、必ず構想のビジョンが先行しています。事実を確認し実証するのは、いつも後のことです。信仰の火花は希望を呼び覚まし、精神を騒がせ、全神経細胞を動員して、目的に邁進(まいしん)せしめます。
19世紀のドイツの化学者ケクレは、多くの化学者たちがいくら研究してもわからなかったベンゼンの構造式として、亀甲(きっこう)形の六角環を夢の中で発見し、現代の有機化学に先鞭(せんべん)をつけました。彼の発見は、研究に研究を重ねて作り上げたものでなく、夢の中に示された幻によって決定したのです。これが有名な、ケクレの科学的発見でした。
また同じころ、ドイツの考古学者シュリーマンは、幼い時に父からいつも聞かされていたホメロスの英雄譚(たん)やトロイ戦役の伝説を証明しよう、と夢みていました。やがて商人として成功し巨万の富を築きますが、ある時、全財産をなげうってトルコに渡りました。荒野となったヒッサリクの丘に、必ず古代ギリシアのトロイの町が埋まっていると確信した彼は、発掘作業に着手し、困難を乗り越えてついにトロイの遺跡を発見したのです。
霊的生命のエネルギー
マグダラのマリヤのように、見えない神の御姿をありありと透視できる人はごく稀(まれ)です。マリヤに臨んでいたエネルギーは、地上の肉なる人間がもっているエネルギーとは別種のものでした。人類の中で聖人といわれるごく少数の人々がもっていた生命の流れ、それは高い清らかな神の生命ともいうべき天的エネルギーでした。
人間は神の子の資質をもつというが、その性質をどうして十分に現すことができないのか。素質があっても、何か大切なものを欠くと、それが表現できない。
私自身が、復活節を前にして何かが自分に欠乏していると思いました。このことは弟子たちにも同様でした。しかし、そこにもキリストは訪れたもう。
その日、すなわち、一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人をおそれて、自分たちのおる所の戸をみなしめていると、イエスがはいってきて、彼らの中に立ち、「安かれ」と言われた。……弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはまた彼らに言われた、「安かれ。父がわたしをおつかわしになったように、わたしもまたあなたがたをつかわす」。そう言って、彼らに息を吹きかけて仰せになった、「聖霊を受けよ。あなたがたがゆるす罪は、だれの罪でもゆるされ、あなたがたがゆるさずにおく罪は、そのまま残るであろう」
ヨハネ福音書20章19~23節
主イエスを失って不安におののき、戸を閉ざしていた弟子たちでしたが、復活のイエスが突如として皆の真ん中に姿を現された時、彼らは俄然、色めきたち、驚喜しました。一体どうしてでしょうか。主イエスは息を吹きかけて「聖霊を受けよ」と仰せになったが、この聖なる御霊こそ、主イエスが「父が約束されたもの」と言われた天来の新生命でした。
「聖霊なんじらに臨む時、なんじら力を受けん。しかして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、さらに地の果てまで、わが証人とならん」(使徒行伝1章8節)とキリストは言われた。
この生命が欠けていると、生きてはいても心は物憂く沈み、暗い灰色の毎日が続きます。しかし微弱な生命でも、これが充実してくると、だれでも現状を打破し、困難や障害を乗り越えて冒険することができます。キリストの与える生命は、単に肉体的な生命以上の高次元の霊的な生命でした。恐怖に意気阻喪していた弱虫な弟子たちは、キリストに出会うだけで、加速度的に生命を注がれて蘇生し、やがて大胆に立ち上がりました。
墓を蹴破る超生命
イエス・キリストは十字架に刑死して、冷たい骸(むくろ)となって墓穴に葬られた。しかし、3日目に彼の死体に新しい生命が脈打ちはじめ、大きな墓石を蹴破って復活された。その復活の生命は、従来の肉なる人間(アダム)には予想もできぬ超自然的な生命でした。このイエス・キリストこそは第二のアダム、霊的新人類の初穂であった。このキリストの超生命は、彼を天にまで昇らしめるエネルギーをはらんでいました。
私たち人間には神の子の素質があるけれど、それだけでは、天国をかいま見たり、天に昇ることはできません。「聖霊を受けよ」と近づきたもうキリストの息吹に触れて、今まで眠っていた魂が急に目覚めはじめます。復活の新生命が私たちのハートに注がれてくると、罪に傷つき、死臭の漂う状態の魂でも、神の子の実存がよみがえる希望があります。
十字架の前夜、主を3度否んで、闇夜(やみよ)に逃げてしまった卑怯なペテロ。また、自分に絶望し、行き詰まっていたほかの弟子たちを賦活(ふかつ)せしめたのは、彼らの主イエス・キリストでした。後に、このペテロたちは聖霊を受けてペンテコステ(注2)的経験を経過すると、もう迫害を恐れぬ大胆な人格に一変して、至るところで聖霊がくだる伝道を繰り広げました。
マグダラのマリヤは、わが主キリストを奪われ、すべての希望が失われた不安と恐れの中で、切実にキリストを求めました。人間が切実な飢え渇きをもって求めない間は、宗教を発見することはありません。つまらぬ享楽に時間を浪費していては、やがて暗い人生の独房の中で寂しく死んでゆきます。
春が来て菜の花畑に白い蝶々が舞い踊っています。暖かい春風に息吹かれると、毛虫がサナギになり、やがて羽化して蝶に変貌(へんぼう)するように、私たちもキリストの息吹に触れ、天にまで跳躍するエネルギーを注がれて、変貌したいと思います。
今日、マリヤのように切実にキリストの面影を慕い求め、「ラボニ!」と呼び求めとうございます。
(1971年)
(注2)ペンテコステ
イエスの復活の50日後、集まって祈っていた弟子たちに聖霊が火のごとくくだり、人格一変した出来事。ここからキリスト教会が始まったといわれる。ペンテコステは、「50」 を指すギリシア語。
本記事は、月刊誌『生命の光』829号 “Light of Life” に掲載されています。